ウネリ:今日は土屋トカチ監督の映画『アリ地獄天国』という映画について話したいと思います。
映画公式サイトはこちら→ 『アリ地獄天国』公式サイト
いま都内で上映されているほか、今月下旬からは横浜でアンコール上映も決まっているそうです。
映画の内容としては、アリさんマークで有名な引越し会社でそこの従業員だった西村さん(仮名)が会社の不当な行為に抗議したいと組合に入ったところ、会社側は営業職だった西村さんをシュレッダー係という奇妙な部署に異動させた。一日中書類をシュレッダーにかけ続けるという過酷な仕事、くり返される誹謗中傷をも耐え抜き、西村さんは労働組合とともに会社と闘い続け…という話です。ウネラさんは、いかがでしたか。

ウネラ:感想を言うとなると、私は非常に複雑な気持ちですね。ただ、本当に大切なことが描かれている映画であることは間違いないと思うので、たくさんの人に観てもらいたいと思っています。日本では労働組合の役割がじゅうぶんに理解されていないと感じます。労働組合の役割と必要性は、多くの人ができるだけ若いうちから知るべきことだと思ってきました。この映画を観ると、そのあたりがよくわかると思います。若い人に観てほしいですね。
ここからは個人的なことで「複雑な気持ち」と言った理由ですが、自分自身も前に勤めていた会社で業務上の問題を抱えてきたのですが、その問題の解決のために労働組合に働きかけるという手段は、結局とらなかったんです。それにはいろいろな理由がありますが、いちばんは自分に起きた問題自体と、それをめぐる会社とのやり取りにほとほとすり減ってしまって、心身ともに闘う気力がなくなってしまったんですね。それ以上会社に居続けたら、自分が壊れてしまう。危機回避のために、ある意味では、徹底した「闘い」は放棄して退職を選んだという経緯があるので、身につまされるところもありました。
ただ、そういう選択でよかった、そうするしかなかったと今では納得できています。私にはその道が合っていたのかもしれないし、一定程度心身が回復したら、また別の表現の仕方があるとも思っています。実際に会社を辞めたことで心身の状態は良くなってきていますし、辞めて生き延びたということを、一面では誇りにも思っています。
ウネリ:そうだね。この映画を観れば、監督の土屋トカチさんも、支援者の人たちも、西村さんにしっかり寄り添い続けていることがよくわかるとおもいます。だからこそ闘い続けることができたのかもしれない。
一方で、多くの人がこうして闘うことすらできずにいる現状があることも事実でしょう。
会社と西村さんとの闘いのストーリーの途中途中に、土屋監督が友人の「山ちゃん」について語るシーンが入ります。これらのシーンは、“涙”の一言に尽きます。監督が私的な感情を思い切り差しはさむ手法は好き嫌いが分かれるかもしれませんが、私はよかったと思いました。ともすれば映画全体が「強さ」「ハードさ」の印象を与える中で、「山ちゃん」のシーンが「優しさ」を注入してくれています。
ウネラ:本当に。私は山ちゃんに感情移入して嗚咽してしまった。
ウネリ:印象深いシーンを一つ挙げるとすれば、西村さんがユニオンと一緒に会社前で「街宣」活動をする場面です。街宣とは、自分たちの考え、主張を路上でアピールする活動です。マイクを握って「会社は不当行為をやめろ!」と訴えるわけです。西村さんたちが街宣を始めると、オフィスビルの窓の閉め切られたブラインドに少しすき間があいて、そこからビデオカメラとか携帯電話とかが出てくるんだよね。中にいる社員がビルの中から西村さんを撮影しているわけだ。トカチ監督が目ざとく気づき、逆にそれをカメラにおさめた。
ウネラ:おぞましい光景だと感じる一方で、「そういう世の中だよね」って冷静に見てしまう自分もいて、なんかつらかったですね。
ウネリ:ぼくは「社員たちはなぜこんなことができるのかな」と首をひねってしまった。みんな家に帰れば、いいお父さんだったりお母さんだったりするわけだよね。その人たちがなぜ、西村さんに対してはそこまで冷たくできるのか。
そう考えたときに、ふと気づいたことがある。それは、現実世界では西村さんが完全なアウトサイダー、マイノリティーであり、ビルの中から西村さんを撮影する社員たちがマジョリティー、健全な人たちと見なされているのかもしれないなということです。
この映画を観ている僕たちは、西村さんにシンパシーを感じている。だからビルの中の社員たちの行動が理解できない。でも、ふだんの街中で、この場面が起きていたら皆さんどう思うか。
残念ながら「デモ」や「街宣」を奇妙なこと、迷惑なこと、と受け取っている人がかなり多くいます。そういう視点が支配的になっている社会だからこそ、ビルの中の社員たちは安心して西村さんの抗議を無視し、無礼にも盗撮まがいの行為ができるのだと思います。
ウネラ:自分が少数派なんだなと感じる瞬間は日常でも多くありますね。私この間、書店でそれを感じたんですよ。特設コーナーで大々的に平積みされている本たちが、とても排他的な内容だったり、ヘイトに満ちたものだったりしたわけです。うわ、と嫌悪を感じたんですが、その直後ふと「こういう本がたくさん売れているのだとすると、私ってもはや完全にマイノリティーなのでは」と思って。
ウネリ:なるほど。私たち一人ひとりができることは何かというと、現実世界で闘っている人を独りにしない、ということだと思います。
先ほどデモや街宣を迷惑なものとみている人が多いと書きましたが、そこまで悪く思っていない人もいるわけですよね。その人たちは何か行動を起こしてほしい。
行動というのは簡単で、たとえ用があっても、少しだけその場に足を止めて、マイクを握っている人の話を聞くということです。それだけで世の中は少しずつ変わってくると思います。西村さんを撮影していた社員たちも、「俺たちのほうが間違っているのかな」と自分たちを疑うようになるかもしれません。
「足を止める」ということが重要だと思うんです。
ウネラ:そうですよね。私も誰かが何かを必死で訴えている時、できるだけ「素通りしない」ようにはしているつもりです。その人が伝えたいことに少しでも耳を傾けたいと思う。その内容に賛同するかどうかは、また別の問題です。「聞いていますよ」「無視しません」という表明は、大事だと思います。なかなかそこまで余裕を持てない時も多いですが。
何においても、誰かが取り残されたようになる状況って嫌だな、という気持ちが私には強くあります。抽象的な言い方になってしまいますが…。声をあげて闘っている人を見ていると、私はちょっと苦しくなってくることがある。多くの人たちに素通りされてもなお声を上げ続ける人の姿を見ていてつらい、という気持ちもあるけど、一方で「自分はああいうふうに闘えなかったな」「もっと声を上げたほうが良かったのかな」みたいなことも思うわけです。コンプレックスです。
でも、声は出せなくても、訴えることができなくても、苦しみながらなんとか今あきらめずに生きている人は、そうして生きていること自体がじゅうぶん「闘い」だと私は思っています。
なので、声をあげている人にはもちろんですが、あげられないで苦しんでいる人たちにも「味方でいるよ」と伝えたい気持ちです。そういうためにブログを書いたりしています。
ウネリ:西村さんは精神的に強いし、本当に粘り強く頑張った人だけど、土屋監督はちゃんと密着することで、西村さんのハードな部分、強い部分だけでなく、人間的に苦しんでいるところもきちんと描いたと思います。
たとえば、シュレッダー係のつらさを弁護士に問われて「むしろその中にどう楽しさを見出すかを考えたので…」というあたり。自分を客観視して他人が動いているかのように考えることで、なんとかつらい状況をやり過ごしていたんですよね。
ウネラ:西村さんはさらっと言っているけど、あれは凄まじい現実を物語っている場面ですよね。
ウネリ:「最終決着」ではないのですが、急転直下で和解の一報が飛び込んできたとき、一報を聞いた西村さんは即座に笑みを浮かべるようなことはなかったんです。むしろ、とても冷徹な表情をしていた。そこに、長年にわたる西村さんの苦しみがはっきりと見えたように思います。形式的なもので割り切れない、心情的な部分です。
ウネラ:その人が受けた傷というのは、消えはしないと思うんですよね。何らかの「決着」をつけることで、傷が癒えていく部分はあると思うし、そうした人々の行動の積み重ねが社会を変えていくことは間違いないと思います。でも、西村さんがここでつけた決着と、西村さんが取り返しのつかない傷を負ってしまったこととは、分けて考えなければならないと思います。闘ってきたこと自体、すごい負担だったということも忘れてはならない。社会的な行動と、個人の内面に関わる部分は、同じ次元で扱うことはできないと思っています。
報道などではやはりその「決着」「結果」の部分にフォーカスしていくし、ニュースとして扱う以上、ある程度そうならざるを得ないと思います。でも、声をあげた個人の心情、内面の部分に思いを馳せることを忘れてはならないと思うし、そこは最大限尊重されるべきことだと思います。土屋監督は時間をかけて被写体を追い続けることで、そこに寄り添って描いていたように思います。「山ちゃん」のことが、大きいのかもしれません。
ウネリ:とにかく日本の多くの会社が従業員に対してとても酷いことをしているのは間違いないことだと、ぼくも一取材者としての経験から断言できます。だからこの会社だけがひどいという結論ではなくて、自分たちが働いている職場の状況に対して、一度疑いの目をもって眺めてみるべきだと思います。こういう映画を観ることで、その問題意識が喚起されるし、その解決策も例示されている、社会的意義のある映画で、特に若い人に見て欲しいと思いました。
最後に一言だけ感想を加えると、エンドロールで流れる音楽が個人的に好きでした。「マーガレットズロース」というバンドだそうなんですけど、エッジの効いたロックバンドだなと思って。他の曲とかも聞いてみたいです。




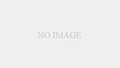


コメント
労働者権利意識がとても高いドイツで暮らしています。そのドイツでも、会社での不当な扱いや圧力は日常茶飯事で、私の周囲を見る限りは、たとえ組合があったとしても、当事者が声を上げることは稀です。私は当事者になったことがなく、傍観者(bystander) として、当事者になってしまった同僚や友人の為に私に何が出来るのか考えることが多いです。当事者にとっては声をあげることは様々なリスクを伴うとともに、そうすること自体多大な努力を必要とするし、それでなくても辛い状況で、更なる行動を取るのは、とても困難なのは見ていてわかります。また、問題が起こると、大抵は当事者と会社の間で秘密裏に話し合いが進められる為、および、こういう事項自体、当事者を守る守秘義務条項にあたるため、当事者以外の人に何が起こっているのか見えない構造になってますよね。実は誰にとっても非常に身近な問題なのにそれが可視化されてないだけなのではないでしょうか。今まで私はたまたま当事者にならなかったけれど、傍観者が当事者をどう支援できるか、これから色んな可能性が出てきてほしいと願います。こういう映画取り上げてくれてありがとうございます。
コメントいただき、ありがとうございます。私は昔、取材先から「ドイツでは、有給休暇を取らない記者は軽蔑される」と聞いたことがあります。その言葉が気に入ったので、同僚たちにもよくそう話してました。そのドイツでも、会社からの不当な扱いや圧力は日常茶飯事なのですね。残念です。日本ではいま、広告代理店最大手の電通が社員を個人事業主化する方針を打ち出しました。こういうことが続くと、トラブルが起きた時はさらに大変なことになるように思います。心配はつのるばかりです。私は過労死やハラスメントの問題を継続的に取材しています。今後も発信していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
牧内昇平