この夏のある日のこと。
学校帰りの長男が、虫カゴを片手にぶら下げていた。
カゴの中をのぞくと、小さな虫が一匹いた。雑草や枯れ葉のすき間に、黒ずんだべっこう飴のような色をしたそのからだを、潜りこませていた。
「コオロギだよ。友だちと空き地で捕まえたんだ。学校の近く」
「ほんとだ。コオロギだね。うちで飼いたいの?」
わたしは小さい頃カエルやカブトムシを飼い始め、ろくに世話もせずに死なせてしまったことがある。それ以来、自分に生き物を飼う資格はないと思っている。家でもしばしばその話をして、子どもと虫捕りをする時は、いつも捕ったそばから放すことにしている。子どもたちも軽々に「飼う」とは言わない。
「ううん。せっかく捕まえたから虫カゴに入れてきたけど、すぐにかえしてあげる」
「そうか。それがいいね。でも、できれば同じ場所にかえしたいよな。明日、学校行ったときにかえしてくればいいよ」
「うん、わかった」
そんな会話をした後、長男は虫カゴをリビングの適当なところに置き、宿題やら工作遊びやらをしはじめた。自分がつれてきた虫を気にかける様子はなかった。
福島に住んで以来、家のまわりの原っぱに行けばバッタやコオロギはいくらでもいる。あまり珍しいものでもない。下の子ども二人も、少し眺めただけですぐに飽きてしまい、虫カゴは部屋のすみに置きっぱなしになった。
この小さな虫が我が家のヒーローになったのは、この日の晩、空が濃墨の色に染まった頃だった。
ちょうど夕ご飯を食べ終わる頃、「リリリリリリ」という音がした。お盆を過ぎた頃だから、窓を開けば虫たちの声はひっきりなしに聞こえる。エアコンをつけていたけど、どこかの窓があいていたかな。でも、少し違うぞ。不思議と少し、クリアな音がするのだ。子どもたちと首をかしげていると、数分後にまた、「リリリリリリ」がはじまった。
そうだ!
虫カゴにみんなの視線が集まる。子どもたちがはじけるように「鳴いてる!」とさけんだ。でも、そのさまを凝視しようと虫カゴを取り囲んだ頃には、鳴き声はやんでしまっていた。
その後もコオロギは家族の不意をつくように鳴いた。鳴き続けるということはなく、長くても十秒くらい。子どもたちが取り囲んでいるうちは鳴かないけれど、目を離すと、「リリリ…」が始まる。子どもたちは興奮してしまい、その夜は布団をしいた子ども部屋に虫カゴを運び、枕元において寝た。
でも、コオロギがわが家のヒーローになったのは、この日限りだった。
乱暴に小さな虫カゴに押しこまれ、弱ってしまったのだろう。翌朝からコオロギはほとんど動かなくなった。学校に行く時、長男は虫カゴを持っていかなかった。下校後も「すんでたところにかえしたほうがいいんじゃない?」と声をかけたが、長男は生返事で動かなかった。ただ、何か気にかかっているのだろう。ふだんはおしゃべりな長男が、少し黙りがちだった。出かけるのが面倒なだけなのか。その日も鳴き声を聞きたくてうちに置いておきたいのか、わたしには分からなかった。いらいらしたが、子どもの反応を待つことにした。
その日の晩、居間に「リリリリリリ」という声は響かなかった。コオロギは動かなくなっていた。わたしは口調を強くして長男を叱った。
「ぜったい、今日じゅうにかえしなさい」
「はい……」
真っ暗だったので、二人で出かけた。学校の近くの空き地までは2キロくらいあり、夜ふけに歩くのはしんどかった。「家の近くのところで、がまんしてもらおうね」と言うと、長男が「うん…」と答えた。それ以外、話すことはなかった。
家のまわりには空き地があちこちにある。少し歩いて、その中でも下草が生い茂り、虫がたくさんいそうな場所にかえすことにした。
「自分でお別れしなさい」と、わたしは突き放すように言った。こわがりの長男はおっかなびっくり、街灯の光がほとんど届かない原っぱの中に足を踏み入れていった。虫カゴのふたを開け、詰めこまれた葉っぱや草とともに、コオロギを土にかえした。
そのとき、長男は小さな声で言った。
「バイバイ……」
そのコオロギにだけ届けばいいという、小さな声だった。あたりが静まりかえっていたので、わたしも聞きとることができた。
その声を聞いてわたしはとても安心した。長男に小さな生き物を弔う気持ちがあることを確かめた気がした。二人で真っ暗な草っぱらに手を合わせ、家に帰った。
心が軽くなったのだろう。帰り道、長男は少し話した。
「おれ、悲しかったっていうか、後悔したんだよ」
「どうして」
「だって、おれがコオロギの自由を奪っちゃったから」
「そうだな」
手をつなぐと、長男の手はふっくらとしていた。
その日は窓を開け放して寝た。月がきれいに出て、虫たちの大合唱が聞こえる。マツムシ、スズムシ、そしてコオロギ……。
「弔う」=「とむらう」。
辞書を引くと、「訪う」という言葉とともに書いてある。
人は、生きている相手を「訪う」のと同じように、死んでしまった人を「弔う」のだ。古い友人に「最近、どう?」と語りかけるのと同じように、もう帰らぬ人に語りかけるのである。ロックミュージシャンでもなければ、死者に向かって語りかける声は小さく、あるいは心の中にとどまって音量をもたない。
だから「黙祷」という言葉がある。
いずれにしても、心の中に死者に語りかける言葉がなければ、すべての弔う行為は意味がない。そこに「弔意」はない。
そして、その言葉はその人自身の心から自然と芽生えてくるもので、誰かほかの人が無理やり引き出すことは、けしてできない。



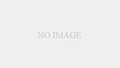





コメント