個人的なことを書く。
先日、運転免許を更新してきた。私が受けたのは「優良者講習」なので、写真撮影や講習を含め、受付から交付まで小一時間で済む、さらっとしたものである。
講習時、教本とともに免許証への臓器提供意思表示を促すリーフレット(日本臓器移植ネットワーク作成)が配布された。
私の兄は3年8カ月の長期脳死状態を経て、24年前に16歳で亡くなっている。そのため私は、脳死と臓器移植について、長い間考え続けているのだが、いまだ個人的にも納得のいく答えを見いだせていない。考えれば考えるほど、混乱する。
兄の症例はやや特異なもので、学術論文でも発表されており、あるデータサイトでは「脳死否定例」として紹介されている。つまり、脳死状態と診断された後に、回復不能とされた一部の脳機能に反応がみられるようになったり、自発呼吸がみられたりという経過をたどったのだ。
こうした反応は良い兆候として歓迎された。しかし私は同時に、言い難い恐怖も感じていた。大学病院で「回復不能」な脳死状態だと診断され、これ以上の治療行為がほぼ無意味だと告げられた時、両親がもし人工呼吸器を止める判断をしていたら、そうした回復を見ることも、その後3年8カ月もの間兄とともに過ごすことも、かなわなかったのだ。
私の母は医療従事者だったし、父は非常に独特な信念を持つ(ある種の変わり者ともいえる)人間なので、医療の専門家が言うことにも屈しなかった。消極的な治療しか見込めない大学病院を見切り、田舎の病院に転院したあと、両親は兄を徹底的に観察し、変化が見られればすかさず医師に報告し、自分たちのほうから積極的な治療や検査を提案していくような様子だった(もちろん、それを採用するかどうか決定するのは医師の側である。それらに真摯に耳を傾け続けてくれた主治医たちには、心から感謝している)。こんなケースは稀だろうと、家族ながら思う。
大病院で「回復不能」と伝えられたら、家族としてはどこかで区切りをつけなければならないと考えるだろうし、そうした複雑で余裕のない心境のなかで「臓器提供」という選択肢を突き付けられたとしたら、どうだろうか。「たとえ臓器の一部でも、この世に生き続けさせたい」とか「いのちを誰かのために活かしたい」といった考えが浮かぶことは、自然なことかもしれない。
しかし私が脳死からの臓器提供を考えるとき、先に述べた、脳死状態の兄と過ごした3年8カ月をどう捉えていいのかという問題が、頭をもたげてくる。多くの人が長期脳死の人の状態を知らないだろうが、その血色はよく、体の動きも見られ、手や顔に触れればあたたかい。兄には排尿や排便もあった。けして、冷たくなった人がたくさんのチューブにつながれてそこに横たわっているだけの状態ではないのだ。だから私はその3年8カ月を、「兄と過ごした」「兄と生活していた」と感じている。
兄のことは脳死状態になった初期から、両親が毎日3時間ごとのバイタル記録とともに詳細な「看護日誌」を残している。いまは私がそれを預かっており、少しずつまとめていきたいと考えている。
私はこの「脳死からの臓器移植」について感じている違和感を、長い間口にすることができなかった。それは脳死状態から臓器を提供した人も、提供を受けた人も、すでに多数存在しているからだ。その人たちの選択を否定する気にはどうしてもなれない。むしろ「傷つけたくない」と思う気持ちが強い。私が自分の体験を交え自分の考えを語ることで、臓器提供にかかわった人たちを苦しませてしまうのではないかと、悶々と葛藤してきた。
兄の死から20年以上が経ち、ようやく脳死と脳死の人からの臓器移植について、さまざまな書物や論文を読み始めている。そしてやはり、脳死状態とは何なのか、脳死を人の死としていいのかという根本部分の議論が、圧倒的に足りないと感じる。
冒頭に紹介した意思表示のためのリーフレットに「家族」という表記が多いことが気になった。「表示をしていないと、もしものときに家族が悩んでしまいます」「家族が悩んだり、迷ったりしないように」「『提供しない』の意思であっても、家族の心の負担をなくし、家族への思いやりにつながります」
とにかく家族と共有し、家族と話し合っておくことが強調されている。それは最終的に移植の承諾が家族に委ねられているからである。いくら本人が「意思表示」していても、その場で「決める」のは結局は家族だ。いくら「軽減される」といっても、ここには非常な苦しみがあるだろう。感じ方、考え方は千差万別だと思うが、私にはその部分がどうしても引っかかる。

また「本人の意思」ばかりがフォーカスされるが、その「本人」はたったひとりでこの世界に生きる存在ではあり得ない。家族や友人、たとえ特別親しくないとしても、よく行くコンビニや食堂の店員や、郵便物や荷物を届けてくれる配達の人、インターネット上の友人など、数えきれない人たちが自分の意思とは関係なく、自分の人生に関わっている。
それなのに、自分の生き死にを自分のサインひとつで決めてしまおうとしていいのだろうか。いのちというのはそこまで「自分ひとりのもの」なんだろうか。
ほかにも書きたいことがたくさんあるが、きょうはここまでで精いっぱいだ。
きのう、近くの花屋で大きな花束をふたつ買った。予算も奮発した。
その数日前から「兄に花でもあげようか」と考えていた。悩んだ末に買ったけれど、そのあとどうしたらいいかわからなくなってしまった。
私はこの花をどこかに供えたいのではないのだ。ここにいない兄に、手から手へ、この花を渡したい。
結局なす術もなく、私は兄の墓へ向かった。誰もいない田舎の墓には気持ちのいい風が吹いていた。誰か先客があったようで、花筒にはすでに花が活けてあった。それらをそっとおさえて、選りすぐった花々を丁寧に挿しているうちに、「あの兄にこの花の良さがわかるわけがない」とか「ずいぶんもったいないことをしてしまった」などと感じられて、おかしくなった。私たちはそういう兄妹だった。
もったいないから、まだ蕾んでいる花を何本か、活けずに持ち帰ってきた。
命日に何かをしたいなんて思えたのは、兄が死んで以来はじめてのことだった。




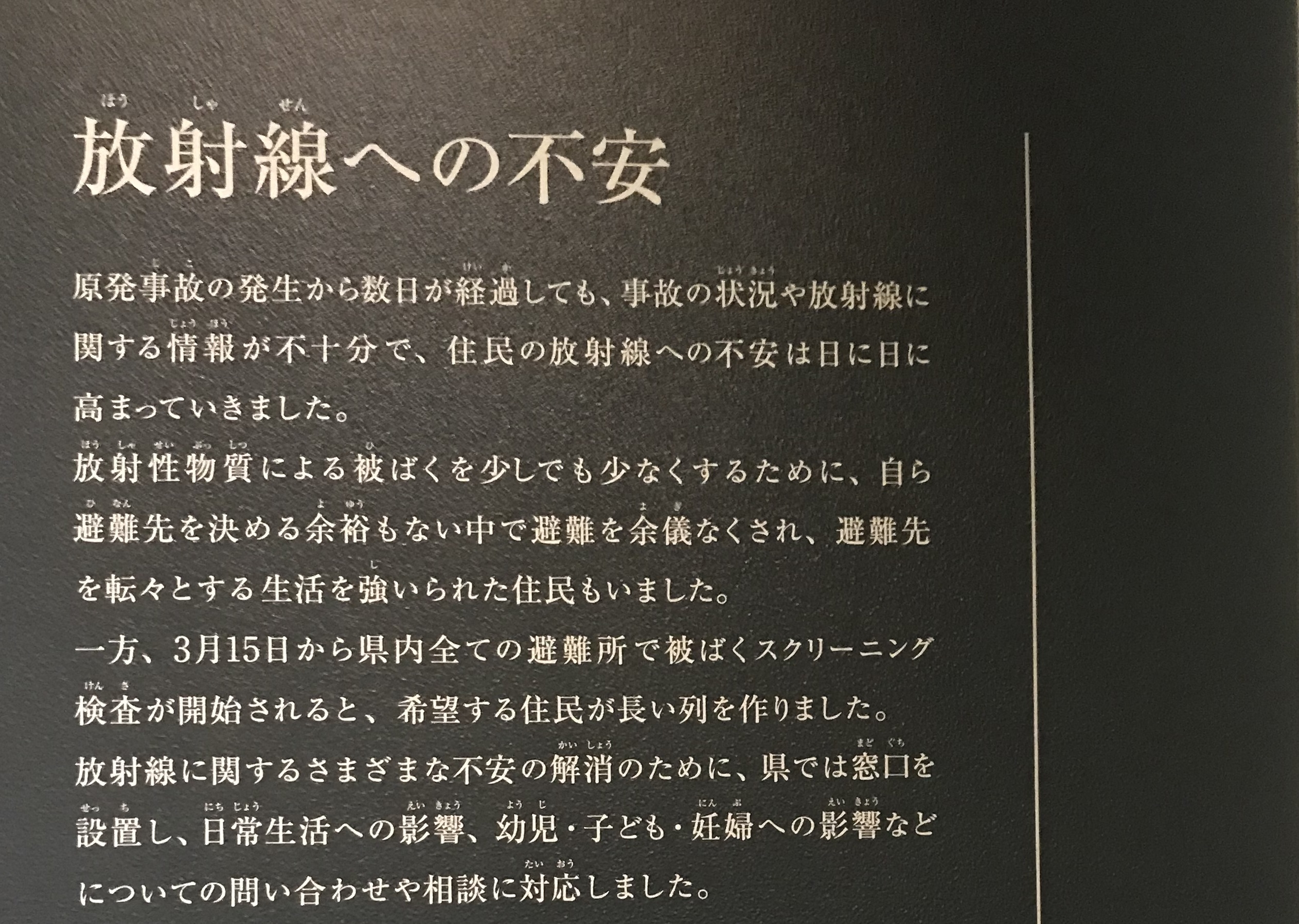



コメント