先日、以下のような記事をアップしました。
コロナウイルスの感染ピーク時に患者数がどれくらいになるのか、厚労省の計算式をもとに、市町村別に推計したものです。
添付記事内のデータは福島県内についてのものですが、リンクしている厚労省の計算式を使って、どなたでも大雑把な数を算出できると思います。
数を出すことの意味
記事内にも書いたように、これらの数字を出すことは特段難しいことではなく、「簡単な計算」です。
今後の感染症対策など、状況によって変化するあくまで概算の数ですが、試算してみると、自分の住む地域の感染リスクを少し具体的にイメージできるようになるのではないでしょうか。
すると、自分の住む地域の医療体制はどうなっているのか、対策は十分とられているのかということが、より明確な疑問となって立ち現れてくると思います。
この試算は、まだ患者が出ていない(表面化していない)地域に、より有効だと考えます。
患者が出てから対応に本腰を入れるのでは、遅すぎる。
専門の医療機関のほか、軽症者の受け入れ施設の確保、相談機関の拡充など、感染拡大後では残念ながら対応が間に合わないという悲惨な状況を、私たちは目の当たりにしています。
たとえば福島県内では39人が感染、死者なし(4月13日時点)という状況ですが、自治体は「現状表面化している患者数」に合わせてではなく、「感染ピーク時の想定される患者数」に見合う対策をとるべきです。自分の暮らすまちで、そうした対策がとられているかどうか。それを知るのは、大切なことだと思います。
その上で「対策が不十分なのでは?」と感じたら、そのことは何らかのかたちで表明すべきだと考えます。
危機的な状況の中で、自治体も努力している。職員は必死で対応をしている。それは事実だと思います。
ただ、「だから迷惑をかけられない」「そんな中へ意見したりすのは気が引ける」という理由で、何も言わないでいるということは、まったく違うと思います。

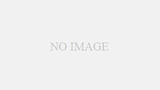


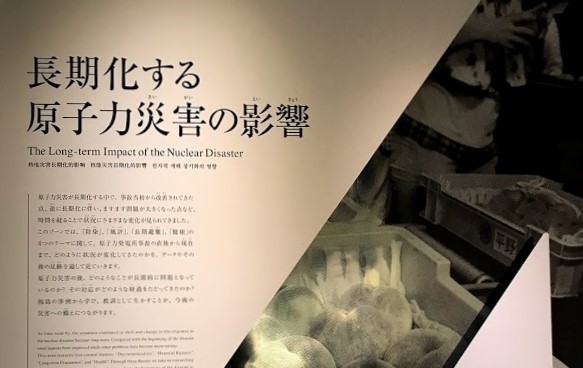

DSC_2746-120x68.jpg)
コメント