新潟市水道局に勤めていた男性職員(当時38歳)が、2007年5月に自ら命を絶ちました。遺族は上司(A係長)からのいじめ・ハラスメントがあったと指摘しています。損害賠償を求める裁判は3月3日、男性の妻Mさんの証人尋問を行いました。筆者は3月5日付でレポートしました。
この件について追加で言及したいことがあり、再度取り上げます。被告(新潟市水道局)側の尋問内容に憤りを覚えたからです。
「刷り込み」と「揚げ足取り」
3月5日付の記事では、被告側弁護士による次のような尋問内容を紹介しました。
被告側弁護士 ●●さん(亡くなった男性)の性格はいかがでしたか?
Mさん 家では明るいし、子煩悩で、家族思いな人でした。
弁護士 (※裁判に提出されている証拠を示す)同僚からは、「拒まれたら断れない。上司に注意されると委縮するタイプ」との評価があります。これをあなたはどう思いますか?
Mさん よく分かりません。
弁護士 プレッシャーに弱いとか、職場が変わると不安定になるとか、そういったことはありませんでしたか?
Mさん 特にないと思います。
亡くなったのは“本人が弱かったから”。こういう印象を刷り込むための質問のような気がして、筆者は違和感を覚えました。
ほかにはこんなやり取りがありました。
弁護士 ●●さんは「徹夜しても終わらない」と言っていたそうですが?
Mさん はい。
弁護士 「毎日徹夜しても終わらない」と?
Mさん はい。
弁護士 徹夜とは、自宅で働くということですか?
Mさん 場所の問題ではなく、職場に行っても仕事が進められない。ということだと思います。
弁護士 つまり、「徹夜」というのは「たとえ話」ということですか?
Mさん どんなに時間があっても仕事が進まない、という悩みの訴えです。
これは「徹夜」という言葉を使った揚げ足取りのように感じました。
被告側尋問の詳細
ここまでが前回3月5日付記事で紹介した部分ですが、ほかにも看過できない尋問内容がありました。たとえば以下です。
被告側弁護士 (妻Mさんがこれまでに提出した書面の中には)『(亡くなった2007年の)3月からは平日の朝食が食べられなくなった。お茶も受けつけなくなった』とありますね。
Mさん はい。
弁護士 この頃から、寝つきが悪く、寝るためにお酒を飲んでいたと。お酒は何をどのくらい飲んでいましたか?
Mさん ほとんどがビールです。350ml缶を2本くらいでした。
弁護士 お酒はほぼ毎日ですか?
Mさん はい。
弁護士 ご家族はその頃、●●さんにどのように対応していましたか?
Mさん 仕事をやめるように言いました。
弁護士 ●●さんのご両親やお医者さんに相談はしませんでしたか?
Mさん 夫はほぼ毎週、子どもたちを連れて実家に帰っていたので、話すのならば本人が話すと思い、私からご両親には話をしていません。
弁護士 知り合いには?
Mさん 知り合いにも相談していません。
妻Mさんへの尋問で被告側弁護士が一貫して指摘したのは、「Mさんが医師らに相談していなかった」ということです。しつこいくらいにそのことをくり返し聞いていました。
弁護士 相談する場として、職場の健康保険組合とか市役所の「心の相談窓口」とかは考えませんでしたか?
Mさん 職場をやめることが大切だと思っていたので、それを一番に優先して考えていました。
弁護士 職場で●●さんと仲がよかった人はいますか?
Mさん ■■さんや▲▲さんです。
弁護士 2007年の4月ごろ、その方たちに相談はしませんでしたか?
Mさん その方たちの番号を知らなかったので、連絡の取りようがありませんでした。
亡くなる2週間ほど前のこと
被告側弁護士は、亡くなる2週間ほど前、2007年4月21日のことも聞きました。●●さんがおもちゃを片付けない子どもを怒鳴ってしまった日のことです。その日の●●さんの様子について、妻Mさんは裁判所に提出した書面で以下のように書いていました。
4月21日の夜、長男(4歳)が遊んだ後おもちゃを片付けないことに夫が怒鳴り、子どもが泣き、夫がさらに怒鳴り、家を出ていきました。1時間ほどしてから帰ってきたのですが、しばらく玄関でしゃがみこんでいました。……怒鳴った後に「ごめん、仕事で俺の頭は壊れかかっているんだ。泣きたいのはこっちの方だよ。心の中で子どもたち以上に俺が泣いているんだ」とも言っていました。
妻Mさんの陳述書
これに対して被告側弁護士は以下のような尋問をしました。
弁護士 「仕事で頭が壊れかかっている。心の中では子どもたち以上に俺が泣いている」。●●さんはこういう言い方をしたんですね。
Mさん はい。
弁護士 それに対してあなたはどのようなことをしましたか?
Mさん 夫が悩み苦しんでいると思いまして、仕事を辞めるようにと、何度も話しました。しかし、夫は『辞められない』と言いました。
弁護士 なぜ、『辞められない』と?
Mさん なぜ、という言葉はありませんでした。
弁護士 2007年3月下旬ごろと、4月21日と、●●さんは少なくとも2回、明らかに異常な状態になっていたということですね。
Mさん 異常というか、限界を超えているんだなと思いました。
弁護士 それに対してあなたは、「仕事をやめて」とアドバイスをしたとのことですね。でも他の人に相談することはなかったんですね。お医者さんにも。医者への相談は考えなかったですか?
Mさん 仕事が根本の理由なので、医者ではなく、まずは仕事を辞めるようにと考えました。
被告側弁護士が指摘したのは、やはり「医師に相談しなかったのか?」ということでした。
被告側尋問の意味を考察する
傍聴メモを読み返すと、被告側弁護士は一回の尋問のうちに何度も、遺族が医療機関などに相談していなかったことを確認していました。第三者に助けを求めなかったことを余程強調したいようでした。男性の(けっして多量ではない)飲酒についても、遺族が止めていなかったことを指摘したいのでしょう。
このような尋問をくり返すのは、彼らが裁判で以下のような主張をしているからだと思います。
原告側は、●●さんを病院に連れて行ったりするなどの行動をすることがなかった。この点において、明らかな精神的変調に気づいていたという原告側には、●●さんの不幸について一定の落ち度がある。
遺族にも一定の落ち度がある――。聞き捨てならない言葉です。
この主張で被告側が狙っているのは、賠償額に「過失相殺」の考え方を適用させることです。
「過失相殺」という言葉は、交通事故の処理の時によく聞きます。乗用車と乗用車が交差点で衝突した。過失割合は、右折車が80%で直進車が20%、というような具合です。
今回の裁判では、遺族は新潟市水道局に対して約8千万円の損害賠償を求めています。新潟市水道局は、仮に水道局の安全管理に非があったとしても、「過失相殺」が適用され、その賠償額は減額されるべきだと主張しているのです。
「遺族にも落ち度」という主張は許されない
読者の皆さんに聞きます。被告側の「遺族にも落ち度」という主張に共感しますか?
筆者は全く共感しません。これを言われた時の遺族の心情を考えると、たとえ法廷の場であっても、水道局はこんなひどい主張をすべきではなかったと考えます。
家族が仕事のことで深く悩んでいるからと言って、誰にでも相談できるでしょうか。相談できる場合と、できない場合とがあると思います。家で酒を飲んでいたとしても、「適度な飲酒が憂さ晴らしになるならば」とは考えないでしょうか。
本人が精神的にひどく苦しんでいる時、家族も平静ではいられないはずです。亡くなった男性の妻Mさんも、当時から何らかの精神的ダメージを受けていたのではないでしょうか。そのような状態で、仮に考え得るすべての対策を講じていなかったとして、それを第三者が責めることができるでしょうか?
筆者はこれまで数十の過労死・ハラスメント死事件を取材してきました。その経験から言えば、家族が自死を防ぐのは非常に難しいです。心配して心配して、毎日夜遅くまで一緒にいても、残念ながら防げないことがあります。心の病は人から正常な判断力を奪います。と言っても、その人をロープで縛りつけておくことはできないでしょう。自死を防げなかったことは「家族の落ち度」だとする考え方を、筆者は許容できません。
ただでさえ、ご遺族は十分すぎるくらい自分を責めているでしょう。「あの時、ああすればよかった」、「自分がああ言わなかったら、亡くなるのを食い止められたかもしれない」。そういうことをたくさん考えているはずです。十分苦しんでいる人をこれ以上苦しめる権利は、誰にもありません。
そもそも、過労死やハラスメント死の裁判で「過失相殺」は主張すべきでしょうか。法律の専門家ではない筆者にはピンときません。遺族の苦しさ、悲しさは極大です。本来なら金銭換算できるものではないはずです。しかし、裁判では「損害賠償」という形で責任を追及するしかない。このため、遺族側はやむを得ず金銭という形での賠償を求めているのではないでしょうか。
遺族が本当に求めているのは、「亡くなった人の命」でしょう。命は金に換えられません。無理やり数字の世界に当てはめようとしても、それは「無限大」としか表現しようがない。無限大のものに「過失割合が何パーセント」という話はふさわしくない。筆者はそのように考えています。
裁判で不当に苦しまされないために
妻Mさんへの被告側証人尋問を傍聴していて、筆者は苦しくなりました。裁判という場が「二次加害」の場になってしまわないかと心配でした。過労死・ハラスメント死の裁判では、被告側(企業など)が遺族の感情を逆なでするような言動をすることがしばしばあります。そのことに対して、筆者は抗議の意を示したいと思います。裁判を起こした遺族が不当に傷つけられることは、防がなければなりません。
こういうことを書くと、逆に、いま裁判を検討している遺族が訴えるのを躊躇してしまう心配があります。「そんなに苦しまされるなら、裁判はしたくない」と思う人がいるかもしれません。筆者もその点を憂慮します。しかし、だからと言って「二次被害」の心配がある現状を隠しておくのは得策ではないと考えます。こうした主張が行われた場合、むしろ積極的に事実を明らかにし、「たとえ法律上可能であっても世の中では通用しない」と明確に意思表明していくことが重要だと思っています。そうしなければ、現状が改善されないからです。
私自身、きょうのこの文章を掲載することには躊躇もありました。この文章がMさんの傷口にさらに塩を塗る恐れもあるからです。しかしMさんは記事掲載を快諾してくれました。「裁判を闘う遺族の心情が少しでも分かってもらえれば」というのが、Mさんの気持ちです。

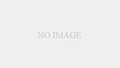






コメント