2007年に長崎市幹部(故人)から性暴力を受けたある女性記者が、市に損害賠償などを求め裁判を起こしています。この裁判の意義や論点は多岐にわたるため、ここですべてを書き尽くすことは到底できませんし、私はこの裁判について直接取材をしていませんので、「取材記事」と呼べるようなものではないということをあらかじめお断りしておきます。
ただ、同じく取材先から性暴力を受けた者として、この事件については以前から注視してきました。
今回、原告の女性や私と同様に取材先から深刻な性暴力被害を受け、かつこの裁判の取材にもあたっている郡司真子さんの協力を得て、自分なりに文章を綴ることにしました。
事件の経緯
女性記者は2007年7月、当時の長崎市幹部(原爆被爆対策部長)から取材中に性暴力を受けたとして、長崎市に対し損害賠償や謝罪を求めています。
報道によると、女性は被害直後から著しく体調を崩しながらも、市幹部に対し、電話で直接抗議。所属する報道機関も市長に抗議し、同年11月1日の長崎新聞紙面に事件の記事が掲載されました。市幹部はそれと時期をほぼ同じくして、自死しています。
事件詳細と裁判の現状については以下の記事に詳しいので、読んでいただきたいと思います。※被害についての詳細な記述も含みますので、心身に不調をきたす可能性のある方は、無理なさらないでください。
https://www.businessinsider.jp/post-189904 (竹下郁子記者 BUSINESS INSIDER 2019年4月26日)
https://www.bengo4.com/c_18/n_13613/ (出口絢記者 弁護士ドットコムニュース 2021年9月28日)
長崎性暴力裁判が問いかけるもの
裁判の証人尋問を前に、先月、新聞労連と原告側代理人弁護士が記者会見を開きました。
その際、郡司さんは、代理人の角田由紀子弁護士と中野麻美弁護士に以下のような質問をしたそうです。
Q この裁判が、日本の報道現場の取材のあり方へどのように影響すると思いますか?
これに対し、両弁護士は以下のように回答しました。
角田弁護士
この裁判がこれから報道取材に与える影響についてですが、女性記者が安全に仕事をするには、どういう領域が必要か、考えなきゃいけないということだと思います。
記者が危険な現場に身を置くということの、危険というのは、今まで戦争の現場ということしか考えられていなくて、本件のような取材現場が危険の範疇に入っていなかった。そのあたりのことを見直していく必要がある。女性の記者が安全に働くためにはどうするのかというのは、報道の側からでも考える必要があるのでないか。なんでもかんでも夜討ち朝駆けで男性と同様に働けば良いということにならないのではないかと思っております。そこは、取材の仕方とか報道のあり方を身の危険という視点から、戦争の現場でないところから、考え直す必要があるんではないかと思います。
中野弁護士
難しい問題ですね。日本の民主主義とか政治のあり方の根幹に関わっていると思うんです。社会を誰が支配しているのかっていう、問題に関わっているわけで、そうそう簡単に答えが出るわけではない。こういう社会の中での取材であるということ、こういう現実の中に真実を手にするために記者が取材活動しているということなんです。
私の仕事もそうですからね、私なら夜討ち朝駆けやっちゃうんじゃないかな。取材のあり方って、社会の構造に関わっているので、どういう問題なのかって、みんなで議論する必要がある。民主主義の動脈でしょ、報道ってのは。その報道のあり方に関わっているわけですよね。
人間関係を作って、夜いろんなお店で情報をとると。あるいは、その過程でお金のやりとりをしたりとかね、真実の情報を取るために必要であるかのように、これで社会が回って来ているということが、本当の意味で民主主義なんだろうかという問題なんだと思います。どういう取材のあり方が本来あるべきなのかっていう理想論というのは捨てないで、どこから変えていけるかという議論をしなきゃいけないと思うんです。
報道のあり方についてもそうだと思います。ここ十数年、報道のあり方も変わって来ていると思いますが、性暴力については、知見をきちんと広めながら、深い認識をみんなが持てるように変えて行かなきゃならないという問題がある。そういうことを問題提起するために、訴訟にきちんと取り組んでいきたいと思っています。
変わるべきは誰なのか
両氏の真摯な回答に、私は希望を感じました。一方で、会見の現場にいた報道関係者は、それを聞いてどう感じたのだろうとも思いました。
女性の記者が安全に働くためにはどうするのかというのは、報道の側からでも考える必要があるのでないか。なんでもかんでも夜討ち朝駆けで男性と同様に働けば良いということにならないのではないかと思っております。
(角田さん)
人間関係を作って、夜いろんなお店で情報をとると。あるいは、その過程でお金のやりとりをしたりとかね、真実の情報を取るために必要であるかのように、これで社会が回って来ているということが、本当の意味で民主主義なんだろうかという問題
(中野さん)
日本の報道機関では「取材相手との距離を縮める」ということが取材の基本としてとかく強調されます。「人間関係」をつくり、「信頼関係」をつくり、「懐に飛びこむ」努力をして「ネタをもらって(とって)こい」というわけです。一見もっともらしく聞こえますが、「人間関係」「信頼関係」をつくるために実際にやっていることは何でしょうか。
警察署に一日何度も挨拶回りをしたり、警察幹部宅を早朝、深夜に訪れて一対一で話す機会をつくること。「懇親会」と称する飲み会を開くこと。為政者を何のためらいもなく「先生」と呼び、朝から晩まで一文字も字にならない「オフレコ」談義にいそしむこと。
これらの一部は私もかつてやってきたことで、けして自分のことを棚上げにしたいとは思いません。
しかし、そのような一般社会とかけ離れたコミュケーション方法で心身を酷使し、飲食や接待、ハラスメントを介さなければ構築できない関係を、果たして本物の「人間関係」だとか「信頼関係」だと呼べるのでしょうか。それらは結局「上下関係」でしかないのではないでしょうか。
そのなかで、人生に消すことのできない傷を負ってしまう人々が数え切れないくらいいることを、報道機関は、権力者側は、社会は、真剣に考えているのでしょうか。
私個人としては、日本の報道機関は公権力を含めて取材対象と癒着せず、対等の関係を築く努力をすべきだし、ハラスメント被害が容易に想定される現場に記者を単独で臨ませることは避けるなど、何がしかの防護策をとるべきだと考えます。
こういうことをいうと「人と人との付き合いなんだからサシ(一対一)でしか本音は聞けない」などというベテラン記者たちの声がガンガン聞こえてきそうです。そうした考えの人を一概に否定するわけではありませんし、それで良いと思っている人たちは個人的にそうしたスタンスの取材を続けていればいいと思います。
ただ、それを組織として社員に強いたり、「それが取材の基本だ」と安易に吹聴することには慎重であるべきだと考えます。その「取材の基本」に忠実に従った結果として被害に遭った人がその後何年、何十年と抱き続ける苦しみに対し、絶対に責任がとれないからです。
報道機関における性暴力被害はずっと続いています。この間、メディア各社がやったことは何でしょうか? 「ハラスメントを許しません」という抽象的なメッセージを発したり、事後対応として相談窓口を設けたり、そういうことがほとんどで、具体的に「こういう取材手法は被害が起きる可能性があるからやめた」といった話は、ほとんど聞きません。そのことを考えると、報道機関における性暴力被害当事者の一人として、大変な苦しみをおぼえます。
性暴力の「二次加害」という言葉があります。一般的には、被害を訴え助けを求めても、周囲が深刻に受け止めなかったり、逆に被害者を傷つける言動をとること、加害者側が居直ったり、事実が公になった時に世間が誹謗中傷を浴びせたりすることを指すと思います。
しかし私は、「 過酷な事件が起きているにもかかわらず、業界組織として具体的な改善措置を取らないでいる 」ということも、「二次加害」のひとつになるのではないかと感じています。
今すぐにできること
以上縷々述べてきましたが、私は改めてこの裁判に立ち上がった女性へ心からの敬意を表します。そして、この裁判が社会に訴える意義は非常に大きく、私たちはそれを受けて変化を起こす主体であらなければならないと感じています。
前述の中野さんの言葉を借りれば「理想論というのは捨てないで、どこから変えていけるかという議論」は今すぐにでも始められることのひとつだと思います。
(ウネラ=牧内麻衣)






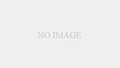
コメント