その日は、朝日がまぶしくて目が覚めた。
仕事部屋ですこし書きものをしていると、子どもたちが一人ずつ起きてくる。目をしばたたかせて机のわきに立ち、声をかけてくれる。
「お父さん、おはよ」
「おはよう」
来る子も来る子も、みんな空を見ていた。きらきらの空を見て、居ても立っても居られなくなったのだろう。三人そろったところで、だれが言い出したということもなく、着がえて近くの公園へ遊びにいった。
こちらもそろそろ朝の支度をしなければと、パソコンを閉じる。妻が洗濯をしてくれていた。ベーコンと卵を焼き、生野菜はサラダに。子どもたちはまだ帰ってこない。それならば驚かせてやろうと思い、妻と二人がかりで、押入れから大きな箱をひっぱり出した。この箱を開けるのは一年ぶりか。いや、去年は余裕がなかったから二年ぶりかな。そんなことを考えた。
大きな箱の中には、小さな箱がいくつか入っている。その中から弓矢や太刀、虎や龍の絵が入った屏風を取り出し、台座に並べる。手狭なわが家には場違いなほどりっぱな兜飾りは、いちばん上の子が生まれて間もない頃、義理の両親がプレゼントしてくれたものだ。贈られた当時はずいぶん場所をとると戸惑ったものだが、年が経つにつれて愛着がわいてくる。
ほほを赤らませて帰ってきた子どもたちは、兜飾りを見つけてちょっぴり驚き、ベーコンエッグの味をちょっぴりほめた。でも、彼らの関心事はもっと別のところにある。小学四年になる上の子が、代表してわたしに聞く。
「で、きょうはどこに行く?」
◇◇◇◇◇◇
車の三列目の座席で子どもたちがしゃべっている。
まん中の子はこの春、小学生になった。となりの弟に向かって、なにやら長い話をしている。
「おれが言いたいのは、いちばん小さいものはないってこと。どんなに小さいものでも、もっと小さいものはあるの。これは、宇宙の外には宇宙より大きなものがあるのと同じ。ねえ、わかる?」
キッズシートに座る末っ子は四歳。にやにやしながらがまんして聞いている。
「それじゃあ、じゅぎょうはここまで。1時間のお休みにします」と言って、まん中の子が話を結んだ。二列目のシートに座る上の子が、「ずいぶんながい話だったな」とあきれた。
きりりと晴れていた空は、車が霊山、飯舘を通りすぎて相馬に着いたころ、少し心配なようすを見せはじめた。相馬の先には太平洋がある。わたしたちは海沿いの道を進み、南相馬の原町へ向かう予定だった。海のほうは快晴だけれど、山の奥のほうに、灰白色の雲があった。まだ小さなかたまりは、少しずつ暗く、大きくなっていくようだった。
空の心配がうつったのかもしれない。車の中では子どもたちが、後ろ向きなことを言いはじめた。
「期待どおり、ではないかもしれないよね」
「すごく小さくて、すぐに終わっちゃったりして」
どうしてそんなこと言うのかなと、こっちは妻と二人でふくれっ面になる。まあいいさ。そもそもテーマパークみたいなものを想像してもらっちゃ困るよ、とハンドルを回す。
そんな諍いごとのあぶくは、目的地に近づいた途端に消えた。
海沿いの道を進むと、子どもたちの歓声がわく。
野原一面に、黄色が広がっていた。
「わー、ひろい。でっかいぞ」
「おはなばたけー」
「あ、なかにひとがいるよ」
◇◇◇◇◇◇
車をとめてスタート地点に向かう。
雲のかたまりは今や大きな壁となって、空の半分を覆うほどだった。白や灰色というよりも、うすむらさき色になっている。とことんあやしい雲行きだ。
でも、子どもたちはもう、そんなことは眼中にない。黄色い花々しか目に入っていない。手をつないで歩きながら、三人で作戦会議を開いている。
「みんなで行くか」と上の子が話す。
「いや、バラバラでいこう。ひとりひとり。競争だ」とまん中。
「よしっ、ぜったいオレが勝つぞ」
「うわあ、緊張してきたな」
四歳の末っ子が兄たちのまねをして、素っとん狂な大声をあげた。
「おおお、きんちょうするぜっ」
一同どっと笑う。
「ぼうやたち、元気だね」と、受付のボランティアの方が声をかけてくれた。「よくきてくれました。ここがめいろのスタート地点です。めいろは二つあります。二つともゴールしたらテントのところに行ってくださいね。プレゼントがありますよ」
子どもたちは声を合わせて、「はーい」。
わたしが「行く前に写真を撮っておこうぜ」と提案した。「ゴールはできないかもしれないからさ」
ボランティアの方が反論する。「お父さんは変なこと言うね。そんなことないよね。みんなゴールできるよね?」
「もちろんっ!」
子どもたちは自信満々でそう言って、スタートの看板をくぐっていった。
◇◇◇◇◇◇
野原いっぱいに黄色い花が生い茂っていて、ひとが一人通れるぶんだけの道がついている。そこは、菜の花でできた迷路なのだ。
花の背丈は大人の腰から肩くらい。しばらく歩くうち、金色の波をかきわけて進んでいる気持ちになってくる。子どもの目には、もっともっと不思議な風景が広がっていることだろう。まん中の子はジャンプすればかろうじて先のほうを見通せるが、末っ子はまったくもって黄色い壁の中である。目が輝いている。出会ったことのない空間にわくわくしているのが伝わってくる。子どもたちがうらやましくなる。
スタートしてすぐ、わたしたち一家は自然と二つのグループに分かれていた。上の子が先頭をずんずん進み、妻がそれに続く。これが第一集団。
二番手グループのリーダーは小学一年生になった、まん中の子だ。その背中を末っ子が追いかける。いちばん後ろをわたしが歩く。
迷路は思ったよりも本格的で、道の分かれめでまちがったほうを選ぶと、ぐるぐる回った末に、もとの場所に戻っている。ほかの家族連れに追い抜かれたと思ったら、その親子が頭をかきながら戻ってきて、「この先は行き止まりでした」と教えてくれたりした。
「こっちだ! みんなこっちへこい」
「うわあ、だめ! いきどまりだ! もどって、もどって」
リーダー役だったはずのまん中の子は、途中から大混乱になった。大声で行ったり来たりしている。その兄のうしろを、末っ子がちょろちょろとついていく。

◇◇◇◇◇◇
それにしてもゴールできないなあ、とだんだん心配になってくる。
何度も袋小路にはまり、なかなか先に進めない。むらさき色の雲はますます分厚く、大きくなってきた。数キロ先がぴかっと光り、ゴロゴロ鳴っている。
「おーい、急げ。カミナリがくるぞ」。迷路のあちこちで大人たちの声が聞こえる。みんな同じことを心配しているようだ。でも、うちの子を含め、主役たちはいっこうに動じない。大人のちょっとした緊迫感がかえっておもしろいようで、花の中をぴょんぴょんとびまわるばかりだ。「うわあ、どっちに行けばいいんだあ」などと言って、笑い合っている。同じ年ごろの子といつの間にか仲良くなって、相談したりしている。
いつまでもぐるぐるしているのを見かねて、ボランティアの方が迷路の中に入り、助け船を出してくれた。
「おーい、そっちは行き止まりだぞ。もう一つ手前を回ってきてね」
「あー、そうだったの? さっきの道だったのかー」などと言いながら、子どもたちはその声に従う。ようやくゴールの看板が近づいてきた。大人たちは、なんとか大雨が降る前に車へ戻れるかなと、胸をなでおろす。
ゴール。
先に着いた妻と上の子が手をたたいている。末っ子が走り寄って妻の腰に抱きついた。まん中の子は、仲良くなった友だちと肩を並べてゴールの看板をくぐった。
わたしたちがゴールするのを待っていた別のボランティアのおじさんが、声をかけてくれた。
「よくがんばったね。それでは、雨も降ってきそうなので、きょうは一つめの迷路で終わりにしましょう。みなさん、テントに行ってくださいね。お菓子があります。花火もあるよ」
やさしい声だった。「ありがとうございます」と一礼し、子どもたちの手を引いてテントに急いだ。空は、もはや一刻の猶予もなくなっている。
おはじきくらいの大きさの雨つぶが、ぽつぽつと帽子のつばをたたいた。
◇◇◇◇◇◇
テントを目指して歩いていると、少し先に、洋風の建物が見えた。ああ、あそこが上野さんのお宅だな、と思った。
上野敬幸さん、48歳。あの新しい家のとなりに、数年前までは上野さん一家の元の家があった。2011年3月11日、巨大な津波が集落を襲った。上野さん夫妻は勤務先などにいて無事だったが、同居していたご両親と、二人のお子さんが流されてしまった。
原発が水素爆発を起こして以来、福島第一原発から20数キロのこの地域から、ほとんどの人が避難した。上野さんはその中で、警察や自衛隊の手も借りずに子どもたちを捜し続けた。小学生だった上の子の遺体は見つかったが、まだ3歳だった下の子は、見つからなかった。
それから十年が経った。上野さんは新しい家を建て、被災した古い家を解体した。家の前の野原に菜の花の種をまいた。この場所に子どもたちの笑顔が戻ってくるようにと、願ってのことだと思う。菜の花の迷路は2013年にオープンし、今ではゴールデンウイークの観光スポットとして、新聞に掲載されるほどになっている。
上野さんとその一家については、『LIFE 生きてゆく』という優れたドキュメンタリー映画がある。わたしは半年ほど前にこの作品を見て、胸がつぶれる思いだった。
映画の中で上野さんが泣くシーンがある。震災から数年後、古い家の解体を決めるシーンだ。
「もし(家が)なくなってしまうと、思い出せなくなっちゃうんじゃないかとか…。」(インタビュアーの笠井千晶監督)
「そういうのも、こわいですよ。正直、もう…、永吏可と倖太郎の声なんて覚えてないもん……」
上野さんはそう言ってむせび泣く。見ているわたしも涙をこらえることができなかった。
映画を見て以来、上野さん一家のことが頭を離れず、わたしは、連休の晴れた日に菜の花畑に行ってみようと思っていた。天気予報には裏切られてしまったけれど、子どもたちは存分に楽しめたようだ。
映画に出てきたお宅を通り過ぎ、テントに向かう列はまた、迷路の中と同じ順番になっていた。上の子、妻、真ん中、末っ子とわたし。気が張っている子どもたちは、しだいに強まってくる雨を気にせず、歌などうたいながら陽気にあるいていた。必死でこらえても、子どもたちの輪郭がぼやけてくる。わたしはポケットから取り出したハンカチで、両目をぎゅっとおさえた。
テントで景品をもらい、走って車に戻るころ、雨はバケツをひっくり返したような降り方になっていた。ずぶ濡れになる寸前だったようだ。二つめの迷路に行かなくてよかった。ボランティアの方々に感謝しなくては。少しだけ勢いが弱まるのを待って(それでも「大雨」と言っていい降り方だったけれども)、車のエンジンをかけた。
◇◇◇◇◇◇
ゆっくり車を走らせていると、雨がようやく落ち着いてきた。すると助手席の妻が、
「さっき、上野さんもいたね」とつぶやいた。
「え、あそこにいたの」
「うん。ゴールのところで声をかけてくれた人だよ」
うかつにも、わたしは気づかなかった。
「ウインドブレーカーを着て、テントに行きましょうって言ってくれた人か。そうかあ、あのひとが上野さんだったのか」
「たぶんそう。わたしも最初は気づかなかったけど、声で分かったよ」
妻はさすがだ。よく見ている。
「あの人が上野さんだとしたら、映画と少し印象がちがうな。前よりも日焼けしてたよね」
「畑かな。この間の記事には、農家って書いてあったからね」
映画によれば上野さんは、震災前は畑仕事をしていなかった。亡くなったお父さんが耕してきた土地を、震災後に受け継いだという。
わたしは上野さんと会っていたのか。「ありがとうございます」とお礼も言ったのに、気づかなかった。ご本人に会えたのだったら、挨拶のひとつでもしたかったかな。でも、これでいいような気もした。
「あの人が上野さんか。とにかく、すごくいい人だってことは分かった」
「そうだね」
それ以上話すとまた涙が出てきそうだったので、だまって運転に集中した。ゴールにいたおじさんの、やさしそうな目を思い出していた。ピーク時より小降りになったとはいえ、篠突く雨が降りつづいていた。
泪雨、という演歌にでも出てくるような言葉が思い浮かんだ。その言葉がいま降っているような雨のことを指すのか、よく知らないのだけれど。
妻も同じようなイメージを抱いたのかもしれない。こんなことを言った。
「わたしは、雨が降ってくれてよかったな。なんかそう思った。あそこで雨が降ってくれて、迷路が途中で終わって。なんとなく、それがよかったなって」
わたしは黙ってうなずいた。
子どもたちは菜の花迷路やその後の大雨に大興奮していた。
「すっごく楽しかった」
「また来たい!」
末っ子は、一人で歩ききったことを自慢していた。
「一回も抱っこしてもらわなかったよ。まあ、抱っこしてもらいたいときもあったけどね」
妙に大人びた口ぶりに、車内が笑いはじける。
◇◇◇◇◇◇
子どもたちにも、菜の花迷路ができたわけを話しておこうと思った。わたしがざっと話すと、妻がうまくまとめてくれた。
「君たちと同じくらいの子が、あそこで亡くなっちゃったんだよ。それを知ったから、きょう、みんなで遊びにきたんだよ。亡くなっちゃった子も、君たちと会えて、一緒に迷路ができて、楽しかったと思うよ。また来年も遊びにきたらいいと思うよ」
バックミラー越しの子どもたちは、珍しく神妙な面持ちをしていた。
わたしは、迷路を歩いているときにさわった、菜の花の感触を思い出していた。
四枚の小さな花びらは可憐な印象を与えるけれど、黄緑色の茎はとてもしっかりしていた。ぎゅっと握ると、たしかな硬さを感じた。ひっぱればたわむけれど、手をはなせばびよんと元に戻った。
しなやかな、芯のつよさ。



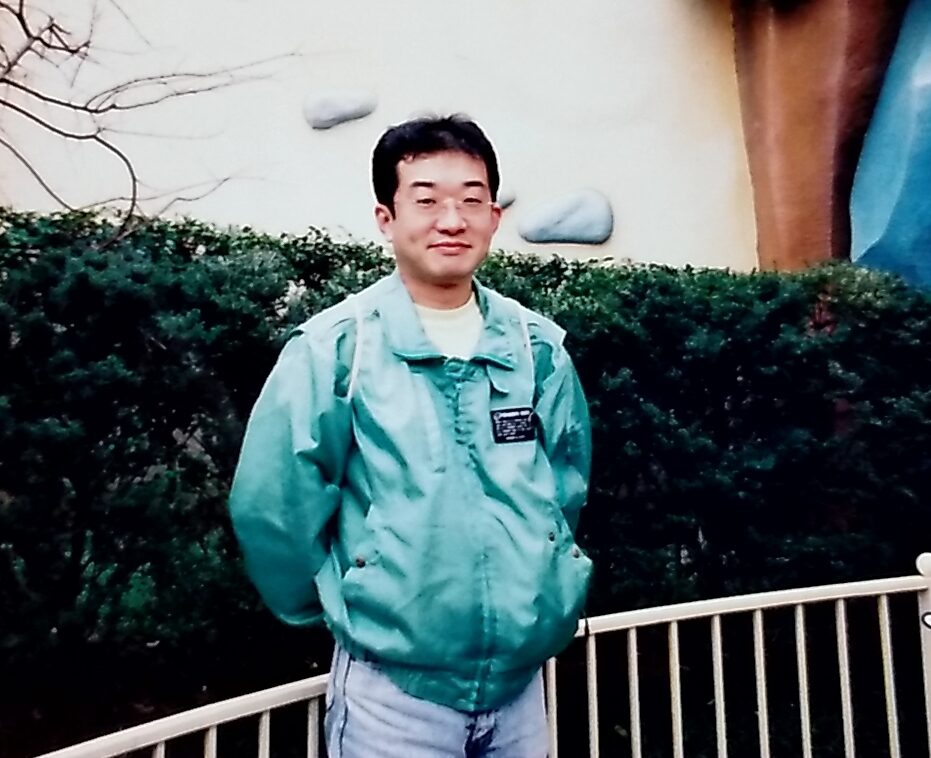
DSC_2254-120x68.jpg)

DSC_2467-120x68.jpg)

コメント
泣きました。私は、子どもたちを追い立てるばかりの母でした。そして、彼は仕事(飲み会も仕事のうちだとも言っていました)ばかりの父でした。時間が取り戻せるなら、こんな休日をたくさんたくさん子どもたちに贈ってやりたかった。
ごめんなさい。
コメントありがとうございます。私たちは褒められた親ではありません。子どもたちの寝顔を見ては、これで良いのかとため息をつく日も多いです。だからこそ、日常のなかでわずかに煌めく瞬間のことを、なんとか捕まえていたい、書き残しておきたい、と躍起になっているのかもしれません。
二瓶さんには、教わることばかりです。どうかこれからも、いろんなお話聞かせてください。
ウネリウネラ