3月14日から三日間、仕事で北海道に行っていた。丸一日列車に揺られて家に帰り、3人の子を寝かしつけてから自分の布団に入った。その1時間後くらいに揺れがはじまった。床から突き上げてくるような衝撃に身を起こし、子ども部屋に走った。
まだリビングでビールを飲んでいたウネラのほうがすばやく動いてくれて、すでに子たちの上に覆いかぶさっていた。その隣から私も覆いかぶさる。緊急地震速報がようやく鳴りだした。揺れは縦方向から横方向に変わり、さらに続く。半開きだったクローゼットのとびらがバタバタと開いたり閉じたりした。倒れそうな洋服掛けをウネラが片手でつかんだ。
いったん揺れがおさまり、目を覚ました上の子とまん中の子が「地震?」と聞いた直後、もう一度大きな揺れがはじまった。さっきよりも大きい。建物のきしむ音が聞こえる。子たちが「こわいよ」「こわいよ」とうめいた。わたしが「だいじょうぶだ」「だいじょうぶだ」と声をかける。が、自分の声も上ずっていたと思う。去年の2月13日地震よりも大きい印象をもった。



わたしは恐怖を感じつつも、不思議と「よかった」という感慨にふけっていた。旅先から帰り着いた後でよかった。この揺れの時に、ウネラや子たちのそばに居られてよかったと、安堵のため息をついていたのだ。みんなと一緒に居られるなら、何が起きても大丈夫だと感じた。
「大丈夫」というのは「危険がない」とか「安全」とかいうことではなく、「何があっても受けとめられる」という意味だ。全くそういう心境だった。たまたまわたしたち5人は親子だが、血がつながっているかどうかなど関係なく、「この人たちと一緒なら何があっても受けとめられる」と思える人たちに囲まれていることが、“幸せ”という言葉の定義の一つのように思った。
大きな揺れはおさまったが、船に揺られているような感覚はいつまでも消えない。いちばん下の子は眠ったままだが、上と真ん中はなかなか寝つけなかった。上の子が話した。
「下からドンっ、ドンってゆれたよね。オレさー、ウクライナみたいにマンションが爆撃されたのかと思っちゃってさー、そういうの想像すると、よけいにこわくなっちゃうよ」
窓の外がぱっと暗くなった。道を挟んだ向かい側の地区が停電したようだ。わが家は無事だった。電気も水も通っている。ウネラが台所の片づけをしてくれていた。わたしは、「こわいよ」「こわいよ」と言い続ける子たちに物語を聞かせることにした。
この日、帰りの新幹線で萱野茂さんの本を読んでいた。そうだ、アイヌの物語、ウウェペケレを話そう。たまたま思いだした「身代わりの美女」という話を自分なりに聞かせた。
むかしむかし、アイヌの若者がいました。きみたちと同じくらい心根のいい若者でした。その人は旅の途中で女の人に会いました。トリカブトの神さまでした。2人が到着した村に、大蛇が襲ってきました。川の向こう岸にまだ尻尾があるのに、こちらの岸に頭が届いてしまう。おどろくほど大きな蛇でした。大蛇が村の娘を食べようとします。そのときトリカブトの神さまが、「わたしが身代わりになります」といいました。若者が神さまを大蛇の口に投げ込むと、大蛇の肉はどろどろと溶けて、巨大な骸骨になりました。無数の骨はやがてバラバラになり、川の水のなかに、じゅわーっと溶けていきました――。
我ながらなぜこんなぶきみな話をと思ったが、パッと思い出したのがこの話だったのだからしょうがない。2人は、「そんなでかいへびはこわい」などとつぶやきながら、話の途中で寝息を立てはじめた。
翌日、小学校は休みになり、家族5人で過ごすことになった。何かしていないと落ち着かないけど、かと言って何も手につかない――。そんな状態だったので、せめて昼はにぎやかにしようと思った。ラーメンやら冷凍のピザやら、子の好きなものを買った。いっしょにタコの頭も買った。地元のスーパーはふだん通りに営業していた。古株の店員がなじみの客と井戸端会議をしている。「ゆうべは大変だったねー」「だいじょうぶだったー?」。こういうやり取りを、とても大事に思った。
ラーメンとピザを食べたあと、みんなでたこ焼きをつくった。上の子がホットプレートに生地を流し、まん中と下の子が丸い穴に1つずつタコを入れる。3人の息が合わず、まだ生地がない穴にタコが転がったり、同じ穴にタコが2、3個入ったり。みんなで笑う。「まだ触っちゃだめだぞ。十分火が入ってからひっくり返せよ」。3人はタコのマークがついた串を片手に、ホットプレートをにらんでいる。でも、なかなか父(わたし)からのGOサインが出ない。待ちきれない3人は、突如歌いおどりはじめた。
たこやきマンボでなんぼ? マンボ!!
たこやきマンボでなんぼ? マンボ!!
こんどは3人の息が完璧に合っている。「たこやきなんぼマンボ」という曲らしい。わたしとウネラは腹をかかえて笑った。子たちを支えようと思いつつ、実際には子たちに支えられているのを実感する。
たこ焼きを食べたあとは公園でドッジボールをした。帰ってくると、テレビで相撲を見た。なんとなく地震のことを忘れかけたころ、夕ご飯の食卓がぐらっと揺れた。あわてて麦茶の入ったびんをつかむ。子たちはテーブルの下に隠れた。震度3。一瞬で現実に引き戻される。
地の揺らぎだけではなく、頭の中には赤黒くやけただれた原子炉のイメージがある。
11年前のことを経験した人たちには、さらに苦しい時間だろうと思う。
「今日は地震がないといいな」と話しながら、子たちは布団に入った。ドッジボールのおかげか、寝つきは早かった。寝顔を見ながらわたしは、アイヌの本に書いてあったことを思い出していた。
萱野茂さんの父、貝澤清太郎さん(アイヌ名、アレッアイヌさん)は筋金入りの狩猟生活者だった。ただ、日本政府に鮭を獲るのを禁じられるなどして、現金収入を得るため炭焼きもやった。ある日、親子で山の中の仕事場に行くと、のこぎりなどの仕事道具が散らばっていた。キツネのしわざだった。それを見たアレッアイヌさんは枯れ枝を集めて火を燃やし、オンカミ(礼拝、祈り)をはじめた。終わるとすぐ道具をまとめて帰り、その日は仕事をしなかった。「今日は仕事を休んで謹慎しますので、どうぞ私どもをお守りください」。キツネのいたずらを「カムイ・イピリマ(神の耳うち)」ととらえ、よくないことが起こる知らせだと考えた――。
茂さんの息子、萱野志朗さんによると、茂さんは原子力発電所のことを「オコッコアペ(恐ろしい火)」と呼んでいた。
参考文献:『完本アイヌの碑』『アイヌと神々の物語 炉端で聞いたウウェペケレ』(ともに萱野茂著)





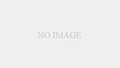


コメント